最近、「チケットを買うとNFTがもらえる」といったNFTキャンペーンが増えています。
しかし、「これって法律的に問題ないの?」と疑問に思ったかたもいるのではないでしょうか。特に、NFTが付いてくる上に、さらに特典グッズまで受け取れるようなケースは、法律知識がないとリスクを見落としがちです。
この記事では、NFTキャンペーンを企画する際に知っておくべき、景品表示法、資金決済法、そして著作権の3つの法律について、具体的な事例を交えてわかりやすく解説します。
■チケット代1万円のNFTキャンペーン、特典グッズはいくらまでOK?
最も関係してくるのが景品表示法(略して「景表法」)です。これは、商品やサービスの購入者に対して、過大な景品を提供することを規制する法律です。
たとえば、1万円のライブチケットを購入すると、NFTが付いてきて、さらに特典グッズがもらえるケースを計画したとします。
景品の上限額とは?
景表法では、チケット代のような「取引価額」に応じて、提供できる景品の上限額が決まっています。
- 取引価額が5,000円未満の場合:景品の上限は「取引価額の20倍」
- 取引価額が5,000円以上の場合:景品の上限は「一律10万円」
今回のケースでは、チケット代が1万円なので、取引価額は5,000円以上にあたります。したがって、提供できる特典グッズの市場価値は最大10万円までとなります。これを超える価値のグッズを提供すると、景表法違反になる可能性があります。
なぜ「NFT」は景品にならないの?
ここで重要なのは、NFT自体を「景品」として扱わないという考えかたです。
NFTはあくまで、ライブの「参加証明書」や「来場記念バッジ」といったデジタルデータとして設計します。これにより、NFTそのものの価値は「0円」とみなされ、景品には含まれません。
もしNFTに、後で他の商品と交換できるような「引換券」としての価値を持たせてしまうと、景品としてカウントされてしまうため、注意が必要です。
■NFTが「電子マネー」とみなされるとどうなる?
こちらは、資金決済法です。これは、SuicaやPayPayのような「前払式支払手段(電子マネーなど)」を規制する法律です。
もし、提供したNFTが「チケットやグッズと交換できる引換券」や「将来の支払いに使える金券」のような性質を持つと、資金決済法の規制対象となり、法律上の手続きが必要になってしまいます。
これを避けるためには、NFTに「引換券」や「利用権」といった機能を持たせないことが重要です。
- NGな例:「このNFTを持っている人は、次回コンサートのチケットが半額になります!」
- OKな例:「このNFTはライブの参加証明です。特典グッズは、参加者全員へのプレゼントです!」
「NFTはあくまで証明・記念」というスタンスを明確にすることが、法律上のリスクを回避する鍵となります。
■キャラクターや音楽を使ったNFT、著作権は大丈夫?
NFTキャンペーンで最も見落とされがちなのが、著作権や肖像権、商標権といった権利関係です。NFTの中身となる画像、音楽、動画、そして特典グッズのデザインには、必ず権利者が存在します。
事前に確認すべきポイント
- 著作権の許諾:コンテンツの制作者や、音楽の演奏者・作曲家など、すべての権利者から利用の許諾を得ているか
- 肖像権:アーティストの顔写真や映像を使用する場合、本人の許諾を得ているか
- 商標権:企業ロゴやキャラクター名など、商標登録されているものを使っていないか
特に、複数のクリエイターが関わるようなプロジェクトや、有名なキャラクターIP(知的財産)を使用する場合は、契約で利用範囲を細かく決めておくことが必須です。後々のトラブルを防ぐためにも、ここは念入りにチェックする必要があります。
まとめ|NFTキャンペーンを成功させるためのチェックリスト
NFTを活用したイベントは、これまでにない新しい体験価値をユーザーに提供できます。しかし、そのためには、法律を正しく理解し、安全な仕組みを構築することが不可欠です。必ず確認したい項目をまとめました。
- □ 特典グッズの価値は10万円以下か
- □ NFTを「景品」ではなく「購入証明・記念」と位置づけているか
- □ NFTに「引換券的な利用権」を持たせていないか
- □ グッズは「参加者全員」として整理しているか
- □ 著作権(音源・画像・動画)や肖像権の許諾を得ているか
- □ 二次流通での利用範囲を明示しているか
- □ 誇大広告(「必ず価値が上がる」等)をしていないか
NFTの仕組みを正しく理解し、法律をクリアしながら、新たなイベントの可能性を広げていきませんか。
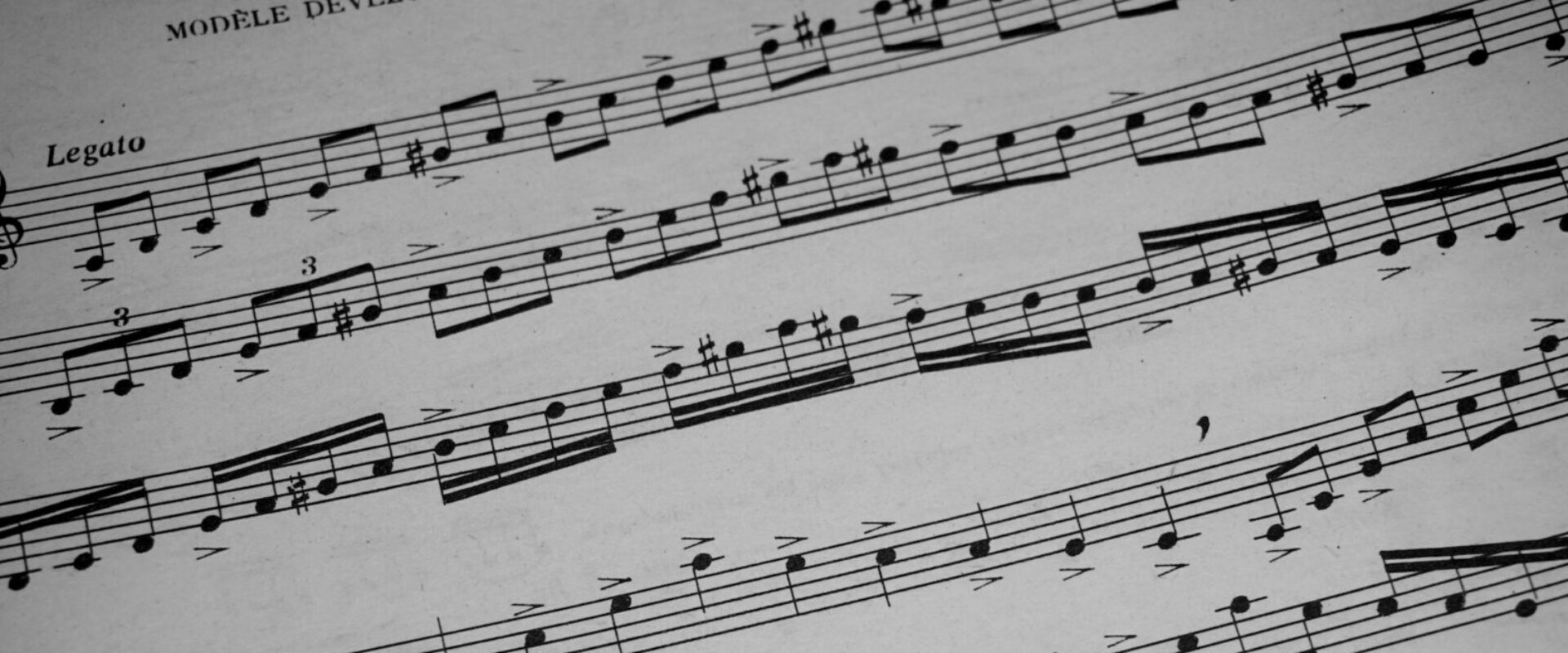
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください。


