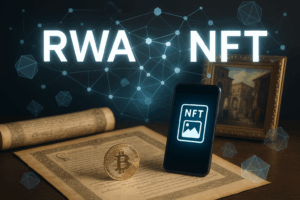決算真っ最中なんですが、1人企業からいよいよ組織化に向けて、いろんなことを進めたり、思考を深めています。
そのひとつが資金調達で、事業計画書やピッチ資料をつくりはじめました。
それらをもとに打ち合わせをすると、いろんな角度から質問が飛んできます。
- 「その数字の前提は?」
- 「本当にその順番で伸びますか?」
- 「強み、差別化はなんですか?」
ぼくはこれを、自分にとっての「複眼」を一気に手にできる、またとない機会だと思っています。
一つひとつの質問に答えながら、
- 思考が浅かったところ
- 見えていなかった角度
- 「なんとなく」で乗り切ろうとしていた前提
みたいなものが、容赦なく炙り出されていく瞬間が何度もくる。
脳内ではスローモーションみたいに、
- なにができていないのか
- それはなぜか
- どうすれば実現できるのか
- なぜ自分たちなら実行できると言えるのか
──これを 24時間ずっと自問自答しつづける電気信号が流れて、同時発火している感覚に襲われる。
そんな時間が続くと、ときどき脳がオーバーヒートする。
今週も恒例の扁桃腺炎で寝込んでいたのだけど、寝てるあいだに見ていた夢を、やたらと鮮明におぼえている。
夢のなかでぼくは、メール画面やSlackのタイムラインを開いたり閉じたりしながら、「できない理由」をきれいに、誰かに説明している。
「ここがボトルネックで、ここがリスクで……」
「ここをこうすれば、出来るようになっていくはずで……」
そんな類のことを論理的に話しているくせに、どこかで自分を冷めた目で見ている自分もいて、目が覚めたときに、ちょっと笑ってしまった。
メタ認知力が高いって、こういう状態のことをいうのかもしれない。
でもきっと、潜在意識レベルで「まだ足りてない」ってことを理解しているのだと思う。
現実と理想のギャップなんて、誰でも抱えているものだけど、「現実的な理想論」をきちんと説明できるのは悪くない。というか、経営陣のしごとはまさにそこで、説明と環境の実現にある。
補完関係とは
ぼくができないことは、杉ちゃんができる。
杉ちゃんが苦手なところは、ぼくができる。
これを補完関係と呼ぶなら、たしかにそうなんだろう。
二人でよく行く飲食店のオーナーにも、
「ほんと、珍しいコンビですよね」
と言われて、うらやましがられたことがあるくらいなので、外から見てもそう映っているのだと思う。
資金調達や事業開発の話をしていると、ぼくが言葉を探しているあいだに、杉ちゃんがスパッと構造を言語化してくれることがある。
逆に、杉ちゃんが「なんかこれ、感覚的におもしろいんだけど」と言ったとき、
「今日の商談でこんな話の展開になってさ」と話し始めたとき、
その感覚を言葉やストーリーに、企画書のかたちに落とすのは、ぼくの役目だったりする。
前からぼくは、
人にはそれぞれ強みがあって、ストレス反応によって強み⇔弱みが入れ替わる
と考えているタイプで、弱みは克服するよりも補い合い、強みを伸ばしたほうがいいと思っている。
そもそも過剰なストレスがたまると、心身に影響が出る。
だからこそ、ぼくは 心=脳のはたらき だと考えて、脳の反応が肉体にでると考えている「心脳一元論」派なので、こういう考えかたをする。
資金調達の「あと」は妥協できない
これから進めていく資金調達では、「そのあと」を妥協しないと決めている。
お金が入った瞬間、会社は一気に変わる。
採用が始まり、人が増え、プロジェクトが同時多発的に走り出す。
だからこそ、
- どんな人と働きたいのか
- どんなカルチャーを守りたいのか
- 何を優先し、何をやらないのか
ここを曖昧にしたまま資金だけ入れてしまうのは、将来の自分たちに爆弾を渡すようなものだと思っている。誰でもいいってわけじゃない。企業文化、いまはまだ暗黙知に近いけど、フィットしない限り、どんな強みも発揮できないのをこれまで何千人と見てきた。
ぼくは、経営は 「組織開発」と「マーケティング」が両輪で、先端をセールスが担っている と考えている。
- 組織開発:どんな「脳」とどんな感情を持った人たちが集まる場にするか
- マーケティング:どんなストーリーで世界とつながりにいくか
- セールス:その最前線で、誰にどんな価値を具体的に届けるのか
この三つがうまく噛み合ったとき、やっと事業は「走り続けられる」かたちになる。とくにスタートアップ/ベンチャー企業は「結果がすべて」なので、ここを外すと痛い目にあう。
どこで頑張るかを決める
事業の進めかたとして、ぼくらが意識しているのはすごくシンプルで、
- すでに伸びている市場に
- 自分たちにとっていいタイミングで参入し
- 自社の強みを活かしたマーケティングを行い
- 便利で、楽しくて、役に立つサービスをつくり
- 熱量の高いチームで
- きっちり計算したうえで、二兎も三兎も追いにいく
というスタンスに近い。
「がむしゃらに頑張る」だけじゃなくて、どこで/何に対して/どの順番で頑張るか を、繰り返し調整している感覚に近い。
複眼思考は、ひとりでは手に入らない
資金調達や事業開発の打ち合わせでは、投資家や株主、パートナー仲間たちから、いろんな角度の質問が飛んでくる。
数字の筋を問われることもあれば、マーケットのリアリティを突かれることもあるし、「そもそも、あなたたちは何を一番やりたいの?」という、どストレートな問いが飛んでくることもある。
しんどいといえばしんどいし、楽しいといえば楽しい。でも、そのたびに自分の「地図」が書き換わっていく感覚がある。
- 見えていなかったリスク
- 口にしていなかった本音
- 「わかっているつもり」だった前提の薄さ
こういうものを、一つずつ確認していく作業は、ときどき痛いし、脳もオーバーヒートする。
それでも、確実に「複眼」を育ててくれる。
ひとりで考えているだけでは、どうしても単眼になってしまう。だからこそ、資金調達のプロセスそのものが、ぼくにとっては思考のトレーニングでもある。
こういうことを言うから、起業家は変態扱いされるんだろうなと思いつつ。
それでもノートPCを開いてしまう夜
19時過ぎに自宅に戻って、小休憩してから、またノートパソコンを開く。
週110時間には及ばないけれど、85時間くらい働いている起業家って、案外多いんじゃないだろうか。
じっとしているほうが不安になる。
回遊魚みたいに動き回って、人と話して、手応えを確かめていたいタイプなのだと思う。
企画へのフィードバック、
「それ欲しかったんです」という声、
「一緒にやりませんか?」という誘い。
そういう一つひとつが、オーバーヒートした脳みそを、もう一回前に押し出してくれる。
生きていることを、脳の奥底から痛感する。
こうして、ぼくの脳の地図が日々更新されていく。
それでも前に進みたいから
ぼくたちルミアデス・ソリューションは、NFTやRWAという新しい領域で、何度も自分に問い直しながら、それでも前に進もうとしている。
脳がオーバーヒートしても、扁桃腺が腫れても、夢のなかでSlackを開いていても。
それでもやっぱり、
「自分たちなら実行できる」
と言えるところまで、思考と行動を積み上げていきたい。