Xで見かけた投稿が、ずっと頭の片隅に残っている。
「かつてのスタートアップは、今よりずっと“夢想家”が多かった」という一節。
たしかにそうだと思う。ぼく自身、過去に2度の起業を経験しているけれど、当時の空気は「まずやってみよう」「まだ誰もやってないことをやろう」という高揚と無謀さで満ちていた。(ちなみに1度目は20年前)
もちろん資金も足りなかったし、仕組みも粗削りだった。でも、いま振り返れば“やってみるしかない”が、何よりの推進力だった。

「スタートアップ」とは、構造を変える挑戦のこと
いまのスタートアップ界隈は、より洗練されている。ピッチデックも資本政策も、採用も、ぜんぶが整いすぎる。リスクマネーの流れ方も変わった。その分外部資本を入れる意味が、昔よりもシビアに問われている。
ルミアデス・ソリューションも、外から見れば“スタートアップ”と呼ばれるのかもしれない。(現時点では2人企業だけどね)
けれどぼくらの感覚では、単なる「成長企業」ではなく「構造を変える挑戦の現場」だと思っている。
NFTやRWAといった領域は、既存の延長線ではなく、新しい経済圏の再設計に近いと捉えている。だからこそ、資本をどう使うか、どこに賭けるかは、慎重でありながらも大胆である必要がある。
外部資本を入れる意味を、もう一度考える
資本を入れるという行為は、単にお金を集めることではない。事業の「速度と射程」を変える決断だといまなら思う。インターネットが時間と距離の制約をなくしたように、資本を入れるということは時間を買うことでもあり、同時に自由を一部手放すことでもある。
ぼくらは2026年にシード、2027年にシリーズA、2028年にシリーズBというフェーズを見据えている。この3年間は、資本を「燃料」としてだけではなく、「構造を変えるレバレッジ」として活用したい。NFT×RWAという文脈では、資本が入ることで取引規模も、信頼の層も一気に厚くなる。
逆にいえば、それを動かすだけの思想と実行力がないと、資本はただの重りになる。
スタートアップの熱量は「共感」と「構想」の掛け算
ぼくと杉ちゃんがよく話すのは、2つ。
「キャッシュポイントをどこに置くか」「その構想に共感できる人が何人いるか」。
NFTを使ったビジネスは、まだ曖昧で理解されきっていない。だからこそ、現場の声や感情、そして信頼を積み重ねることが、資本よりも先に必要だと思っている。
共感が生まれる構想には、資金調達よりも強いドライブがある。それがスタートアップの本質的な熱量なんだと思う。
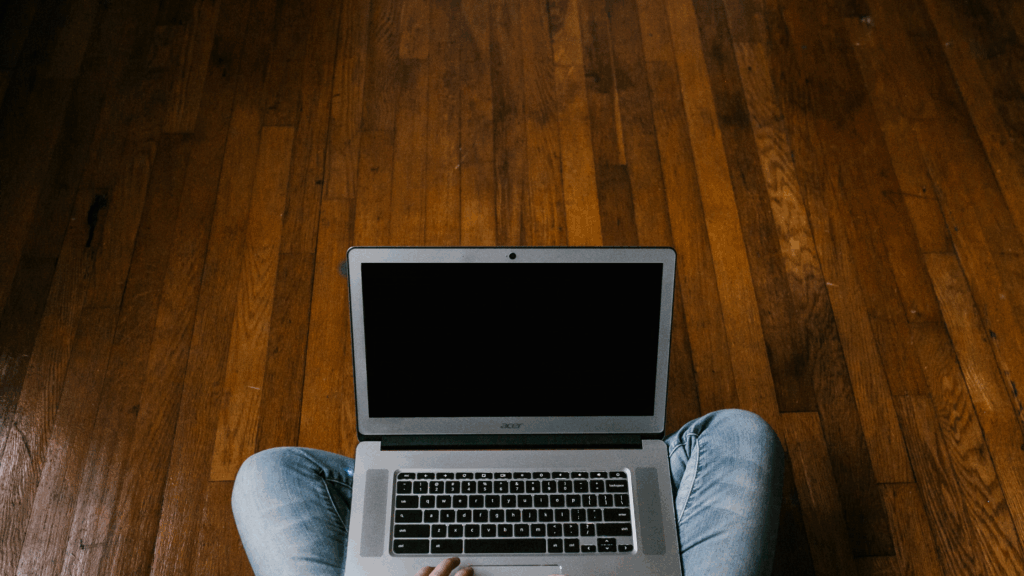
ぼくらが向かう方向
先週の土曜日は引きこもって資料作成。
日曜日はひさしぶりに動画三昧で脳のリフレッシュをした。昨日は夕方から昔なじみと会食(とはいわないか)。
正直、かなり疲労は蓄積している。脳が脈をうっているかのように感じる。実際は電気信号の処理が遅延しているんだろうけど。でも、回遊魚のように動き回って話しているほうが、手応えを体感できる。いつだって事業の立ち上げ期は想像以上に体力も気力も削られる。だけど、誰かと話すたび、「これは本当に必要とされているんだな」と実感する。
そして思う。
スタートアップとは、資金を集める素早いEXITを目指すだけではなく、信頼と構想を集めること。
資本を入れるとは、挑戦のスピードを上げること。そしてその先で、「経済構造を少し変えてしまう」こと。
それができるなら、ルミアデス・ソリューションは間違いなくスタートアップと呼べる。
それ以外のラベルなんて、どうでもいいのかもしれない。
投稿者プロフィール

- 代表取締役社長
- 16歳からバンド活動をおこなう。22歳を機に音楽から離れ、1993年 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア)入社、2000年株式上場後に退社。スポーツデータ・コーポレーション創業に参画。2003年、ファンサイド株式会社創業 取締役、同年10月、個人事務所設立。2005年コミュニケーション・ウェイ株式会社創業。翌年、企業合併により株式会社ワークスエンターテイメントへ商号変更 代表取締役社長。2010年退任。2013年個人事業主として活動。2016年 攻城団合同会社創業 業務執行社員副社長。2024年、個人事務所を株式会社ルミアデス・ソリューションとして現職
最新の投稿
 ルミアデスの日々2026年1月30日会心ノ一撃
ルミアデスの日々2026年1月30日会心ノ一撃 NFT Drop2026年1月30日体験を、一生モノに。NFT Emotion
NFT Drop2026年1月30日体験を、一生モノに。NFT Emotion NFT Drop2026年1月29日NFT Drop活用事例 #5 消えゆく響きを、色あせない「NFT」へ
NFT Drop2026年1月29日NFT Drop活用事例 #5 消えゆく響きを、色あせない「NFT」へ NFT Drop2026年1月28日NFT Drop活用事例 #4 耳元でささやく、世界でひとつの「宝物」
NFT Drop2026年1月28日NFT Drop活用事例 #4 耳元でささやく、世界でひとつの「宝物」


